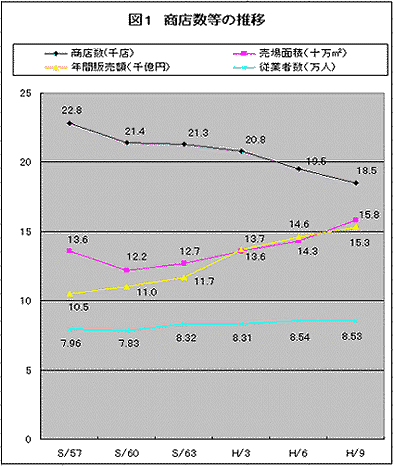商店数 1,000店弱 (△5.0%)減少
売場面積 15万m2(10.6%)増加 |
|
県統計調査課は平成9年6月現在で実施した商業統計調査の結果を発表した。この調査は3年に1回全国規模で実施されるもので、今回発表されたものは速報である。また、この調査は卸売業と小売業に区分しているが、ここでは小売業に的を絞り、商店数、売場面積等の推移、さらにはこれらの広域生活圏別の状況を概観した。
なお、今回の調査から「コンビニエンス・ストア」「専門スーパー」の定義について、売場面積、営業時間に関して変更があった。
図1は昭和57年から今回の調査までの商店数、売場面積、年間販売額及び従業者数の推移を表している。
まず、商店数からみれば、昭和57年までは増加を続け2万2千店余りに達したが、昭和60年の調査で初めて減少に転じた。その後も毎回減少を続け、前回の調査では2万店をきった。そして、今回の調査でも減少率は若干低下したものの歯止めがかからず1千店弱減少し、18,564店になった。これは最も商店数が多かった昭和57年当時に比べれば81.1%であり、この15年間で約2割も減少している。
また、この表にはないが、商店を日本標準産業分類別でみれば、多い順に飲食良品小売業7,496店(構成比40.4%)、その他の小売業5,754店(同31.0%)、織物・衣服・身の回り品小売業2,376店(同12.8%)となっている。
なお、従業者規模別商店数の推移を若干後述する。
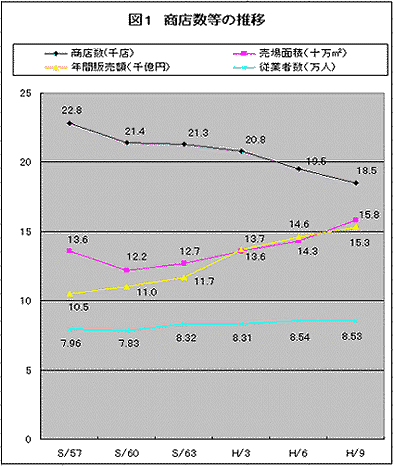
商店数が漸減を続ける中にあって、売場面積は昭和60年を除き、商店数の減少に反比例するような形で漸増を続けている。特に、今回の調査では前回の調査で過去最大の面積になったが、それに比べ15万㎡(前回比10.6%)も増加し、153万㎡に達している。この面積は当然調査を開始して以来の最大の面積であり、郊外型大型店舗の出店等にみられるとおり商店数が減少している実態と重ね合わせてみれば商店の大型化傾向を如実に表わしている。
この調査を開始以来順調に増加してきた年間販売額は、前回の調査において1兆4千7百億円余りとなったが、今回の調査でも消費需要が低迷した3年間にもかかわらず、7百億円余り増加し初めて1兆5千億円を超えた。前回の調査に比べた増加額は7百億円強でその伸び率は5%であり、この3年間の消費者物価指数の伸び率2%弱を大きく上回る増加率となっている。
前回の調査において微増(2.7%)した従業者数は、73人減少(前回比△0.1%)しただけでほとんど変化がなかった。
参考までに小売業とは異なり卸売業における従業者数は、商店数の大幅な減少もあって2,500人余り(同△7.1%)も減少している。
表1は、今回を含む過去3回の従業者規模別商店数の推移である。商店数は昭和60年以降引き続き減少しており、その共通点は従業者数が少ない商店の減少割合が高いことである。前回の調査では従業者数「1~2人」と「3~4人」で10%近い減少率で、それ以上の規模では逆に増加した。しかし、今回の調査では減少した商店の従業者規模は前回までのものに加えて「5~9人」でも減少し、減少する商店の従業者規模がより大きいものにまで拡大している。また、従業者規模「30~49人」でも減少しているが、これは従業者数規模がより大きなものの増加率が平均を大きく上回っていることから50人規模以上ののものに移行した結果と推定される。それ以外の規模では増加しており、特に「50~99人」では、前回の調査に引き続き増加率は著しい。この規模の商店が増加した理由は、既存商店の大型化と平成6年までほどではないものの大型店の新規出店が背景と思われる。
表1 従業者規模別商店数の推移 (単位:店、%)
| 従業者規模 |
平成3年 |
平成6年 |
平成9年 |
| 実数 |
構成比 |
実数 |
構成比 |
対前回増減 |
増減率 |
実数 |
構成比 |
対前回増減 |
増減率 |
| 1~2人 |
11,887 |
57.1 |
10,710 |
54.8 |
▲1,177 |
▲9.9 |
9,970 |
53.7 |
▲740 |
▲6.9 |
| 3~4人 |
4,867 |
23.4 |
4,448 |
22.8 |
▲419 |
▲8.6 |
4,227 |
22.8 |
▲221 |
▲5.0 |
| 5~9人 |
2,739 |
13.2 |
2.860 |
14.6 |
121 |
4.4 |
2,755 |
14.8 |
▲105 |
▲3.7 |
| 10~19人 |
879 |
4.2 |
990 |
5.1 |
111 |
12.6 |
1,071 |
5.8 |
81 |
8.2 |
| 20~29人 |
223 |
1.1 |
250 |
1.3 |
27 |
12.1 |
257 |
1.4 |
7 |
2.8 |
| 30~49人 |
146 |
0.7 |
169 |
0.9 |
23 |
15.8 |
165 |
0.9 |
▲4 |
▲2.4 |
| 50~99人 |
46 |
0.2 |
75 |
0.4 |
29 |
63.0 |
86 |
0.4 |
11 |
14.7 |
| 100人以上 |
30 |
0.1 |
31 |
0.1 |
1 |
3.3 |
33 |
0.2 |
2 |
6.5 |
合 計 |
20,817 |
100.0 |
19,553 |
100.0 |
▲1,284 |
▲6.2 |
18,564 |
100.0 |
▲969 |
▲5.0 |
広域生活圏別に商店数と年間販売額の推移をみたものが表2と表3である。
まず、表2の商店数であるが、前回の調査では全体の減少率△6.2%を超えて減少したものは両磐と久慈の2生活圏でだけであった。しかし、反対に今回の調査ではこの2生活圏の減少率は全体の減少率△5.0
%を下回った。今回の調査で減少率が全体を上回ったものは岩手中部、釜石、宮古、二戸の4生活圏に増え、商店の減少傾向の広域化がうかがわれる。減少率が全体を上回ったものでも釜石を除いてはその程度はさほどでもない。釜石の場合は、そのおかれている厳しい状況を反映し、減少率は△8.4%(商店数では△144店)と極めて高い。
今回の調査で減少率が全体より少なかったものは、前回の調査で全体の減少率を上回った久慈と両磐の2生活圏のほか3生活圏である。
表2 広域生活圏別商店数の推移 (単位:店、%)
| 従業者規模 |
平成3年 |
平成6年 |
平成9年 |
| 実数 |
構成比 |
実数 |
構成比 |
対前回増減 |
増減率 |
実数 |
構成比 |
対前回増減 |
増減率 |
| 盛 岡 |
5,726 |
27.5 |
5,385 |
27.6 |
▲341 |
▲6.0 |
5,135 |
27.7 |
▲250 |
▲4.7 |
| 岩手中部 |
2,773 |
13.3 |
2,626 |
13.4 |
▲147 |
▲5.3 |
2,476 |
13.3 |
▲150 |
▲5.7 |
| 胆 江 |
2,137 |
10.3 |
2,005 |
10.3 |
▲132 |
▲6.2 |
1,933 |
10.4 |
▲72 |
▲3.6 |
| 両 磐 |
2,388 |
11.5 |
2,159 |
11.1 |
▲229 |
▲9.6 |
2,065 |
11.1 |
▲94 |
▲4.4 |
| 気 仙 |
1,556 |
7.5 |
1,495 |
7.7 |
▲61 |
▲3.9 |
1,437 |
7.7 |
▲58 |
▲3.9 |
| 釜 石 |
1,813 |
8.7 |
1,719 |
8.8 |
▲94 |
▲5.2 |
1,575 |
8.5 |
▲144 |
▲8.4 |
| 宮 古 |
2,023 |
9.7 |
1,904 |
9.7 |
▲119 |
▲5.9 |
1,806 |
9.7 |
▲98 |
▲5.1 |
| 久 慈 |
1,165 |
5.6 |
1,079 |
5.5 |
▲86 |
▲7.4 |
1,042 |
5.6 |
▲37 |
▲3.4 |
| 二 戸 |
1,236 |
5.9 |
1,161 |
5.9 |
▲75 |
▲6.1 |
1,095 |
5.9 |
▲66 |
▲5.7 |
| 合 計 |
20,817 |
100.0 |
19,533 |
100.0 |
▲1,284 |
▲6.2 |
18,564 |
100.0 |
▲969 |
▲5.0 |
表3は、広域生活圏別年間販売額の推移を表している。これも前回の調査からみれば、全体の増加率6.2%を上回ったものは、大きい順に久慈、盛岡、気仙であった。逆に下回ったものは、少ない順に岩手中部、二戸、宮古等であった。今回の調査では、唯一盛岡が前回に引き続き全体の増加率を上回り、この地域の消費需要の底堅さがわかる。胆江も大きく上回り最高の増加率になったが、胆江が全体の増加率を7.2%も上回った理由は、この地域に出店した大型店によるものが大きな原因と推定される。反対に全体を下回ったものは、少ない順に釜石、宮古、久慈、気仙と沿岸全域にわたる生活圏である。特に釜石は、商店数の減少率も目立って大きかったが、年間販売額も前回の調査に比べ唯一マイナスに転じ、この地域における経済情勢の厳しさをうかがい知ることができる。
表3 広域生活圏別年間販売額の推移 (単位:店、%)
| 従業者規模 |
平成3年 |
平成6年 |
平成9年 |
| 実数 |
構成比 |
実数 |
構成比 |
対前回増減 |
増減率 |
実数 |
構成比 |
対前回増減 |
増減率 |
| 盛 岡 |
4,999 |
36.4 |
5,485 |
37.6 |
486 |
9.7 |
5,837 |
38.2 |
352 |
6.4 |
| 岩手中部 |
2,111 |
15.4 |
2,188 |
15.0 |
77 |
0.3 |
2,257 |
14.8 |
69 |
3.2 |
| 胆 江 |
1,456 |
10.6 |
1,507 |
10.3 |
51 |
3.5 |
1,691 |
11.1 |
184 |
12.2 |
| 両 磐 |
1,370 |
10.0 |
1,413 |
9.7 |
43 |
3.1 |
1,495 |
9.8 |
82 |
5.8 |
| 気 仙 |
707 |
5.2 |
766 |
5.3 |
59 |
8.3 |
778 |
5.1 |
12 |
1.6 |
| 釜 石 |
914 |
6.7 |
964 |
6.6 |
50 |
5.5 |
950 |
6.2 |
▲14 |
▲1.5 |
| 宮 古 |
977 |
7.1 |
993 |
6.8 |
16 |
1.6 |
997 |
6.5 |
4 |
0.4 |
| 久 慈 |
574 |
4.2 |
634 |
4.4 |
60 |
10.5 |
643 |
4.2 |
9 |
1.4 |
| 二 戸 |
617 |
4.5 |
624 |
4.3 |
7 |
1.1 |
650 |
4.2 |
26 |
4.2 |
| 合 計 |
13,725 |
100.0 |
14,574 |
100.0 |
849 |
6.2 |
15,298 |
100.0 |
724 |
5.0 |
なお、参考までに全国における前回と今回の調査の増減率を本県のそれと比較すれば、商店数は全国△5.4%で本県が△5.0%、売場面積は全国5.9%で本県が10.6%である。年間販売額は全国3.1%で本県5.0%、従業者数は全国△0.4%で本県△0.1%である。
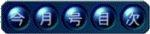
|